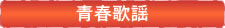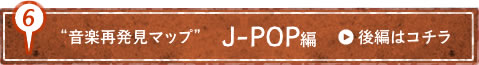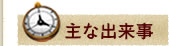- 『三人娘人気』
-
- 元祖三人娘:美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ
- 三人娘人気…1955年、美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみが揃って東宝映画「ジャンケン娘」に出演したことを契機に、同年齢の3人が三人娘として呼ばれ、人気を博した。その後日本の芸能界に数々登場することになる「三人娘」の元祖的存在に。三人娘の基礎は彼女たちによって作られた。
流行歌の時代
- 『ウエスタンカーニバル旋風』
-
- ロカビリー3人男:山下敬二郎、平尾昌晃、ミッキー・カーチス
- ウエスタンカーニバル旋風…1958年2月8日、東京・有楽町の日劇で第1回ウエスタンカーニバルが開かれた。以来、2月8日は「ロカビリーの日」と制定。当時、大人気のロカビリー3人男、山下敬二郎、平尾昌晃(当時は昌章)、ミッキー・カーチスらが出演。彼らが大きなアクションで歌いだすと、熱狂した少女たちによりステージ上にテープや花束が投げ入れられた。60年代のウエスタンカーニバルではGSが活躍。その後、77年8月まで開催された。
- 小坂一也、飯田久彦
- 『裕次郎人気』
-
- 石原裕次郎
- 裕次郎人気…1956年、兄・石原慎太郎原作の映画「太陽の季節」で日活からデビューした石原裕次郎。
「太陽の季節」のヒットと共に、大きな注目が集まった。さらには同作から“太陽族”なる言葉が生まれ社会現象に。ヘアスタイルでも”裕次郎刈り”がブームとなる。続く、主演映画「狂った果実」「嵐を呼ぶ男」で人気を確実なものにして押しも押されぬスターに。以来、俳優、歌手で活躍し、昭和を代表する大スターとなる。
- フランク永井、水原弘
- 島倉千代子
- 田辺靖雄、坂本九
- 田代みどり、森山加代子、西田佐知子、弘田三枝子、木の実ナナ
- ダニー飯田とパラダイスキング
- 『漣健児のカバーポップス』
- 漣健児のカバーポップス…60年代はカバーポップスの時代であった。その黄金時代を築いたのは新興楽譜出版社(後のシンコー・ミュージック)の専務取締役だった草野昌一氏。音楽出版社を経営する傍ら、漣健児(サザナミケンジ)として訳詞を手がけた。最初の作品は、坂本九「ステキなタイミング」(1960年)。その他、飯田久彦「ルイジアナ・ママ」、中尾ミエ「可愛いベイビー」などヒット曲を連発。総数は400曲を超える。
- 『元祖御三家』
-
- 御三家:西郷輝彦、橋幸夫、舟木一夫
- 元祖御三家…60年代に人気を博した西郷輝彦、橋幸夫、舟木一夫の3人を総評して御三家と呼んだ。三人娘同様、70年代に一世を風靡した郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎が新御三家と呼ばれたことから、後に元祖御三家とも呼ばれるようになった。戦後、高度成長期に差し掛かり、日本人が余暇を楽しむ余裕がではじめた頃、一般家庭にテレビが普及し、女性たちが夢中になれるアイドルが出現した。
- 望月浩、三田明
- 『若大将ブーム』
-
- 加山雄三
- 若大将ブーム…東宝で1961年からスタートした「若大将」シリーズの主役に抜擢され、役者、歌手として人気者になった加山雄三。それを決定的としたのは、66年公開「エレキの若大将」とその挿入歌「君といつまでも」の大ヒット。一説にはその売り上げは300万枚を超えたといわれる。その結果、若大将ブームなる現象を生みだした。若大将シリーズは1961年から71年まで全17作が作られた。加山雄三は元祖自作自演アーティストとしての一面もある。
- 青山和子、奥村チヨ、コロムビア・ローズ(二代目)、九重佑三子、本間千代子、吉永小百合
- いしだあゆみ、和田アキ子、由紀さおり、青江三奈、ちあきなおみ、佐良直美、ピンキーとキラーズ
- 『クレイジーキャッツ人気』
-
- ハナ肇とクレイジー・キャッツ
- クレイジーキャッツ人気…50~60年代に人気を博したコミックバンド。正式にはハナ肇とクレージーキャッツ。50年代後半から、「おとなの漫画」、「シャボン玉ホリデー」などのテレビ出演をきっかけに人気が爆発。62年の「ニッポン無責任時代」からは映画へも本格的に進出。
無責任シリーズ、日本一シリーズ、クレージー作戦シリーズ等々、多くの作品が作られ、どれも大ヒットを記録した。「無責任一代男」などの主題歌も軒並みヒット。映画、テレビ、舞台、レコードなど、全てにおいてトップレベルの人気を誇った。
- 『GS旋風』
-
- ジャッキー吉川とブルー・コメッツ、ザ・スパイダース、ザ・サベージ、ザ・ワイルドワンズ
- GS御三家:ザ・タイガース、ザ・テンプターズ、オックス
- GS旋風…GSとはグループ・サウンズという和製英語の略称。66年のビートルズ来日を契機に、エレキギターを抱えたバンドが多数デビュー。当初、人気を博したスパイダース、ブルーコメッツ、サベージ、ワイルド・ワンズがシーンを形成していたところに、67年にザ・タイガース、ザ・テンプターズ、オックスのGS御三家がデビュー。ブームを拡大させ、歌謡界の一大勢力となった。ピークは1967年から1968年にかけてのわずか1年間程だったが、後の日本の音楽シーンに大きな足跡を残した。
- ザ・ピーナッツ、梓みちよ、西田佐知子
- 東芝三人娘:小川知子、奥村チヨ、黛ジュン
- スパーク3人娘:伊東ゆかり、中尾ミエ、園まり
- 『渡辺プロの時代』
- 渡辺プロの時代…60年代から70年代にかけて「渡辺プロなくしては歌番組やバラエティ番組は作れない」と言われるほどの影響力を誇った。初期はザ・ピーナッツ、クレージーキャッツ、スパーク3人娘(中尾ミエ、伊東ゆかり、園まり)、ザ・タイガースといったタレントが全盛期を支えた 。70年代以降は沢田研二、布施明、森進一、小柳ルミ子、天地真理、キャンディーズ等のスターを抱え、多くのヒット曲のほかテレビ番組も多数制作。今日の芸能界の礎を築いた。
- ザ・フォーク・クルセダーズ
- <URC>五つの赤い風船、遠藤賢司、岡林信康、加川良、斉藤哲夫、高石友也、高田渡、友部正人、中川五郎、はっぴいえんど、六文銭
- <ベルウッド>小室等、西岡恭蔵、あがた森魚、高田渡、加川良、なぎら健壱、遠藤賢司
- <カレッジフォーク>森山良子、荒木一郎、マイク真木
- 『自作自演の時代へ』
- 自作自演の時代へ…歌謡界や芸能界のシステムが構築されていく一方で、若者による自作自演の音楽が関西フォークを萌芽として生まれていく。さらにはラジオの深夜放送をメディアとして人気を拡大。その象徴的なヒットが高石友也の「受験生ブルース」、ザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」。その後、岡林信康、高田渡、遠藤賢司といったアーティストがフォーク・シーンを牽引して、自作自演の礎を作り、70年代の本格的なムーブメントにつながっていく。
- ザ・ゴールデン・カップス 、ザ・モップス
- 『サイケデリックムーヴメント』
- サイケデリックムーヴメント…60年代後半にサンフランシスコを中心に起こり、世界中に飛び火。日本の音楽シーンにも少なからず影響を与えた。GS後期を支えたモップスのデビューの際に付けられたキャッチコピーは「日本最初のサイケデリック・サウンド」。その他、ゴールデン・カップスなどが日本でのサイケデリックムーブメントを牽引した。
- フォーリーブス、フィンガー5
- 『元祖アイドル、郷ひろみ』
-
- 新御三家:郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎
- 元祖アイドル、郷ひろみ…1972年にシングル「男の子 女の子」でデビュー。元々は当時所属していたジャニーズ事務所の人気グループ、フォーリーブスの弟分だったが、デビューするやいなや、女の子に間違えられるほどの可愛らしいルックスで大ブレイクし、この年のレコード大賞新人賞を獲得。その後、同世代の西城秀樹、野口五郎と共に新御三家としてお茶の間のアイドルに。特に郷ひろみは、今に続くアイドルのあり方の原型を作った。
- にしきのあきら、清水健太郎、狩人
- 岡崎友紀、浅田美代子、麻丘めぐみ
- 新三人娘:南沙織、小柳ルミ子、天地真理
- <渡辺プロ所属>アグネスチャン、キャンディーズ、太田裕美
- フレッシュ三人娘:榊原郁恵、清水由貴子、高田みづえ
- 『“スタ誕”の功績』
-
- 花の中三トリオ:山口百恵、桜田淳子、森昌子
- <代表的なスター誕生出身者>ピンク・レディー、岩崎宏美、石野真子
- スタ誕の功績…スター誕生は1971年に日本テレビ系で放送開始されたオーディション番組。視聴者参加型のスタイルは当時新しく、徐々に人気番組になっていく。放送終了まで12年間で応募総数が約200万通、予選参加総数が約60万人、番組出場者総数が5500組、うち決戦大会出場者総数が423組、プロデビュー者は81組を数えた。第一号の合格者は森昌子。山口百恵、桜田淳子、岩崎宏美、ピンク・レディー、石野真子、小泉今日子、中森明菜、岡田有希子など多くのスターが輩出された。
- <フォーライフ&ユイ>吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげる、小室等、かぐや姫、イルカ
- 『日本語ロック論争』
- 日本語ロック論争…70年代初めに起きた「これからのロックは日本語で歌うべきか、英語で歌うべきか」という日本語とロック音楽の関係性についての論争。雑誌「新宿プレイマップ」(1970年10月号)、「ニューミュージック・マガジン」(1971年5月号)の座談会が発端。参加者は中村とうよう、内田裕也、ミッキー・カーチス、大滝詠一、松本隆、福田一郎、小倉エージ、折田育造。
- <アルファレコード>ハイ・ファイ・セット、荒井由実、GARO
- 『フォークから
ニューミュージックへ』 - フォークからニューミュージックへ…70年代に入ると吉田拓郎、井上陽水が大ブレイクを果たし、フォークがメジャーなジャンルとして台頭。4畳半フォークという言葉に象徴されるように、当初フォークは叙情的な音楽を指したが、荒井由実がブレイクした1975年あたりから、ニューミュージックという言葉が生まれ、洗練された最先端の音楽というイメージができあがっていく。
- <キティレコード>小椋佳、RCサクセション、来生たかお
- <東芝EMIエキスプレス>
オフコース、アリス、ダウンタウン・ブギ・ウギ・バンド、サディスティック・ミカ・バンド、松任谷由実、チューリップ、甲斐バンド
- 『ポプコンの功績』
-
- <ヤマハ>中島みゆき、谷山浩子、八神純子、チャゲ&飛鳥、石川優子
- ポプコンの功績…ヤマハポピュラーソングコンテストとは、ヤマハ音楽振興会の主催で1969年から86年まで行われたフォーク、ポップス、ロックの音楽コンテスト。略称「ポプコン」で、自作自演系アーティストの登竜門的存在であった。ここからデビューしたアーティストは「あなた」で200万枚の売上げを記録した小坂明子をはじめ、谷山浩子、八神純子、渡辺真知子、中島みゆき、世良公則&ツイスト、長渕剛、チャゲ&飛鳥、あみんの岡村孝子など、日本を代表するシンガーソングライターを多数輩出。それまで、テレビの音楽番組はほとんど歌謡曲系歌手で構成されていたが、ポプコン出身のアーティストが積極的にテレビ出演をするようになり、ニューミュージックをお茶の間に浸透させた。
- ロック御三家ほか:Char、原田真二、ツイスト/キャロル、矢沢永吉、さだまさし、加藤登紀子、松山千春、海援隊、五輪真弓、ゴダイゴ、サザンオールスターズ
- 尾崎紀世彦、沢田研二、堺正章、布施明、中村雅俊
- 山本リンダ、欧陽菲菲、辺見マリ、あべ静江、研ナオコ、ジュディ・オング、大橋純子、ヒデとロザンナ
- 『筒美京平の時代』
- 筒美京平の時代…筒美京平は60年代後半から作曲家活動を始め、最初はGSのヒット曲を手掛けていた。その名前が広く知られるようになったのはいしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」と尾崎紀世彦「また逢う日まで」の大ヒットから。以降、70年代は南沙織、郷ひろみ、麻丘めぐみ、野口五郎など、80年代は近藤真彦、小泉今日子、C-C-B、少年隊などのアイドルのヒット曲を多く手がけていく。売上げ枚数は7000万枚を超え、日本の作曲家の総売上げで1位。
- 『阿久悠の時代』
- 阿久悠の時代…阿久悠は広告代理店勤務から、放送作家として活動する傍ら作詞家をスタート。モップスの「朝まで待てない」をきっかけに本格的に作詞家として多くのヒット曲を生み出す。70年代には「また逢う日まで」(尾崎紀世彦)「北の宿から」(都はるみ)「勝手にしやがれ」(沢田研二)「UFO」(ピンク・レディー)「雨の慕情」(八代亜紀)でいずれもレコード大賞を受賞。また、日本テレビのオーディション番組「スター誕生」では、番組企画や審査員として関わり、多くのスターを輩出。2007年に死去するまでに作詞した楽曲は5000曲を超え、7000万枚近い売上げを記録。日本の作詞家の売上げ枚数1位。
- 『ジュリーこと沢田研二黄金期』
-
- 沢田研二
- ジュリーこと沢田研二 黄金期…60年代後半にザ・タイガーズのボーカルとしてデビューを果たした沢田研二。バンド解散後PYGを経てソロになると、ロック的要素を重視したスタイルでお茶の間に進出、トップスターとして人気を博した。ピークは75年の「時の過ぎいくままに」の大ヒット、77年「勝手にしやがれ」でのレコード大賞受賞から80年代前半まで続き、「サムライ」「ダーリング」「LOVE (抱きしめたい)」「カサブランカ・ダンディ」「OH!ギャル 」「TOKIO」「恋のバッド・チューニング」「ス・ト・リ・ッ・パ・ー 」等々、毎回完成度の高い楽曲と奇抜なファッション性で話題を集めた。歌謡曲とロックを融合させた重要人物とされている。
- 『ザ・ベストテン放送開始』
- ザ・ベストテン放送開始!…1978年~89年にかけてTBS系で毎週木曜日の夜9時から生放送されていた音楽番組。全盛期には視聴率40%超を記録、音楽番組としてかつてないほどの影響力を誇った。チャートいう概念を定着させ、音楽はラジオで聴くものからテレビで見る時代に移行していく。なかでも田原俊彦、松田聖子、中森明菜、近藤真彦、チェッカーズなど80年代アイドルとの関係は深く、番組の顔だったと言っても過言ではない。レコードからCDへという音楽メディアの変化の中、昭和から平成に向かうバブル絶頂期に惜しまれつつ終了した。
1980年代へ続く。
J-POPという言葉が登場する80年代後半も含めて乞う御期待!
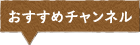



![音楽x映像チャンネルで空間演出STARDAM[スターダム]](https://www.stardigio.com/wp-content/themes/wp_stardigio/common/img/logo-stardam-pc.svg)